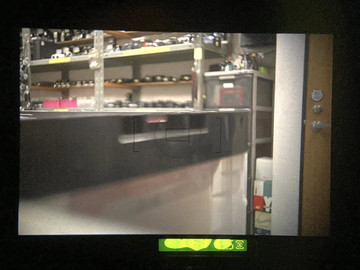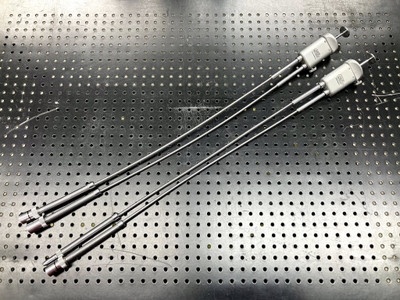私の知らない我楽多屋
1992年1月18日の我楽多屋の写真が発掘されました。
今の店の真下、1階にあった時です。2階へ移動したのは2012年3月なので、1階の店自体はわたし二代目も知っています。私がこの業界に入ったのが1994年4月、我楽多屋で働くようになったのは1998年。
画像の中の我楽多屋は私の知らない店内ですし、外観もテントなどが私が働くようになる前の仕様。
店内に立っているのは、我楽多屋で働いていた沖氏。当時は年配男性がもう1人働いていました。
この頃をご存知のお客さん、どのくらいいらっしゃるでしょうか?
- 我楽多屋のFacebookページ(https://facebook.com/garakutaya.camera)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。
- 更新は少ないですが…X(旧ツイッター)(https://twitter.com/arrowgarakuta)とインスタグラム(https://www.instagram.com/arrow.camera_garakutaya/)もあります。