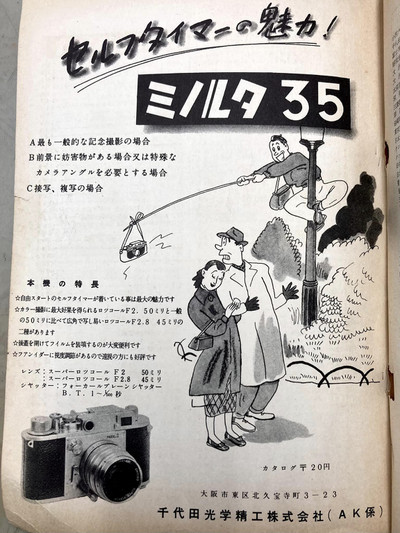エルモフレックス
「エルモ」というと~8ミリのシネカメラや映写機の印象が強いんですけど、スチールカメラの二眼レフ「エルモフレックス」もボチボチと見掛けます。
ただ、今回改めて知って言われてみれば~なんですが、エルモってスチールカメラは二眼レフしか作ってないんですね。
そのエルモフレックス、初号機の登場は戦前の1938年まで遡ります。以後、1955年までの間に細かい仕様の違いを含めて約10機種ほど登場した模様。
画像の個体は1955年(1954年かも)登場の「V」型と思われます。中期以降のエルモフレックスの特徴と言えるのが、ピントフード。
普通にピントフードを開いてウエストレベルで見る方法(下の画像参照)は、①ピントスクリーンを直視するのと、②ルーペを出して拡大して見るのと、2つのスタイル。これが出来る二眼レフは他にもたくさんありますよね。
ポイントはアイレベルで可能な2つのスタイル(下の画像参照)。ピントフードの前板が2段階に倒れるようになっているので、①深く倒して素通しでフレーミングするスタイルと、②少し浅く倒して後ろ板にあるレンズの入った接眼部を覗くと、前板の裏にあるミラー経由で見えるピントスクリーンでピント合わせが出来るスタイル。
ローライフレックス(後期)もアイレベルでフレーミングと拡大ピント合わせが可能なピントフードが付いていますが、両方出来る二眼レフは案外と少ないものです。
- アローカメラ&我楽多屋のFacebookページ(http://www.facebook.com/arrowcamera)も合わせてご覧いただけると嬉しいです。
- 更新は少ないですが…X(旧ツイッター)(https://twitter.com/arrowgarakuta)とインスタグラム(https://www.instagram.com/arrow.camera_garakutaya/)もあります。